離れて暮らす外国籍の親御さんが、日本で独居のまま亡くなられた…。
突然の訃報に戸惑い、何から手をつけていいか分からないというご家族は少なくありません。
日本人の場合と異なり、外国籍の方の死後の手続きには「大使館・領事館への連絡」や「在留資格の抹消」など、特有の対応が必要になります。言葉や文化の違いも重なり、不安を感じられる方が多いのが現実です。
この記事では、外国籍の親御さんが日本で独居のまま亡くなられた場合の流れを、ステップごとに分かりやすく解説します。
目次
✅ 最初の対応チェックリスト
- 警察からの連絡に対応する
- 大使館・領事館にすぐ連絡する
- 死体検案書を受け取る
- 葬儀・遺体搬送の方針を決める
- 死亡届と在留カード返納の手続きを行う
1. 警察からの連絡と、最初にやること
独居で亡くなられた場合、最初に親御さんを発見するのはご家族以外(近隣の方、ケアマネージャー、大家さんなど)であるケースが多く、その時点で警察に通報されます。
そのため、最初に家族へ連絡するのは警察であることが一般的です。
- 警察は検視・検案を行い、死因に不審な点がないか確認します
- 医師によって「死体検案書」が発行されます(死亡診断書に相当)
⚠️ この段階で 最も大切なのは「大使館・領事館」に連絡すること。
大使館・領事館は、自国民が海外で亡くなった場合に必要な法的手続きや本国への遺体搬送について支援してくれます。
2. 葬儀と遺体の取り扱い
遺体の扱いは、故人の宗教・文化やご家族の希望により異なります。
日本国内で葬儀を行う場合
- 日本の葬儀会社は、キリスト教・イスラム教など、各宗教に対応できるところがあります
- 小規模な家族葬や火葬式も選べます
遺体を本国へ搬送(空輸)する場合
- エンバーミング(防腐処理)や特別な棺が必要
- 死亡診断書、防腐処理証明書、非感染症証明書などの書類が必要
- 航空貨物扱いのため、費用は高額になる傾向
遺骨を本国へ送る場合
- 日本で火葬し、遺骨を本国に送る方法が一般的
- 火葬許可証、埋葬証明書、遺骨証明書などを添付して搬送
3. 死亡届と在留資格の手続き
死亡届
- 故人が亡くなった日から 7日以内 に、市区町村役場へ提出
- 死体検案書を添付
- 多くの場合、葬儀会社が代行可能
在留カードの返納
- 故人の在留カードは、死亡から 14日以内 に出入国在留管理局へ返納する義務があります
- 返納を怠ると、法律上の罰則があるため注意
4. 自宅(賃貸・持ち家)の処理
賃貸物件の場合
- 大家さんや管理会社へ死亡を連絡
- 賃貸借契約の解除
- 遺品の搬出と原状回復が必要
- 保証人や保証会社との調整が必要になるケースも多い
持ち家(分譲マンション・一戸建て)の場合
- 不動産は「相続財産」となる
- 相続人が決まり次第、登記名義を変更
- マンションの場合は管理組合にも死亡の報告
5. 銀行口座・年金・保険の手続き
銀行口座
- 口座は死亡が確認されると凍結
- 解約・払戻し後、本国へ送金する場合は国際送金手続きが必要
年金・健康保険
- 年金事務所へ「年金受給者死亡届」を提出
- 日本と本国との間に社会保障協定がある場合、「脱退一時金」を請求できるケースあり
- 健康保険証は返却が必要
6. 相続と遺産の手続き(国際相続)
国際相続では、日本の法律と故人の本国の法律が交錯するため、非常に複雑です。
- 相続人の範囲や割合が国によって異なる
- 日本にある財産(預金、不動産など)は、日本の法律が適用されることが多い
- 本国の相続人との連絡調整が必要
まとめ
日本に住む外国籍の親御さんが独居で亡くなられた場合、
- 警察からの連絡に対応し、死体検案書を受け取る
- 大使館・領事館に必ず連絡する
- 葬儀や遺体搬送の方法を決める
- 死亡届と在留カード返納を行う
- 自宅、銀行、年金、相続の手続きを進める
という流れで進んでいきます。
文化・言語・法律の壁がある中で、これらの手続きをすべてご家族だけで進めるのは大きな負担です。
当事務所では、在留資格関連の届出、相続放棄や遺産分割協議書の作成、国際相続に関する専門家の紹介 などを通じてサポートを行っています。
突然の出来事に直面してお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
📞 お気軽にご相談ください
- ✅在留資格取得に関するサポート
- ✅中国語対応可能
- ✅元警察官による信頼と安心の対応
📍埼玉県さいたま市|全国オンライン相談可


メール:info@okonogikei-gyousei-office.com













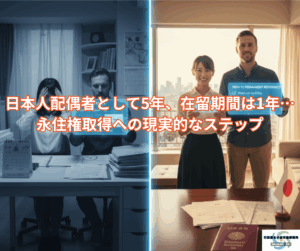
コメント