
外国人を雇いたいけど、技能実習と特定技能の違いが分からない…



どちらが自社に合っているの?
そんなお悩みをお持ちの企業様へ。
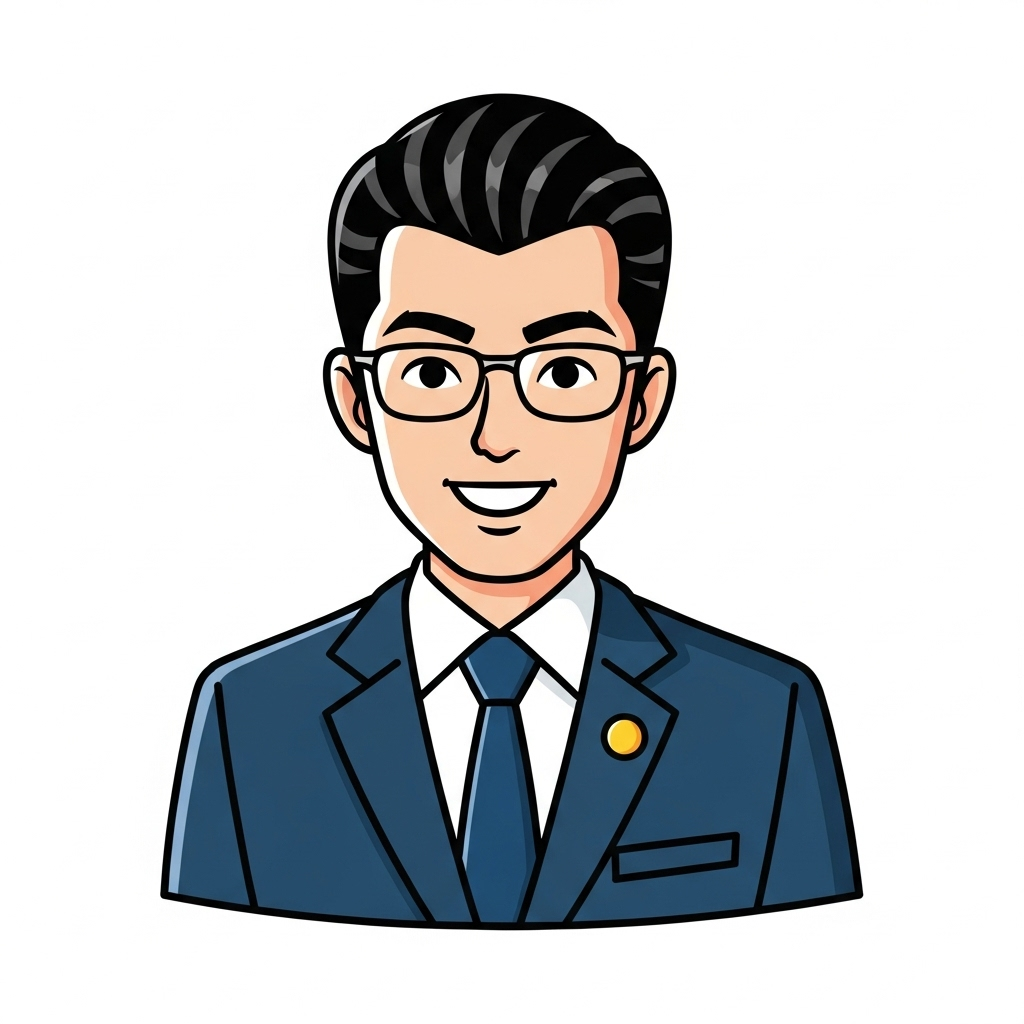
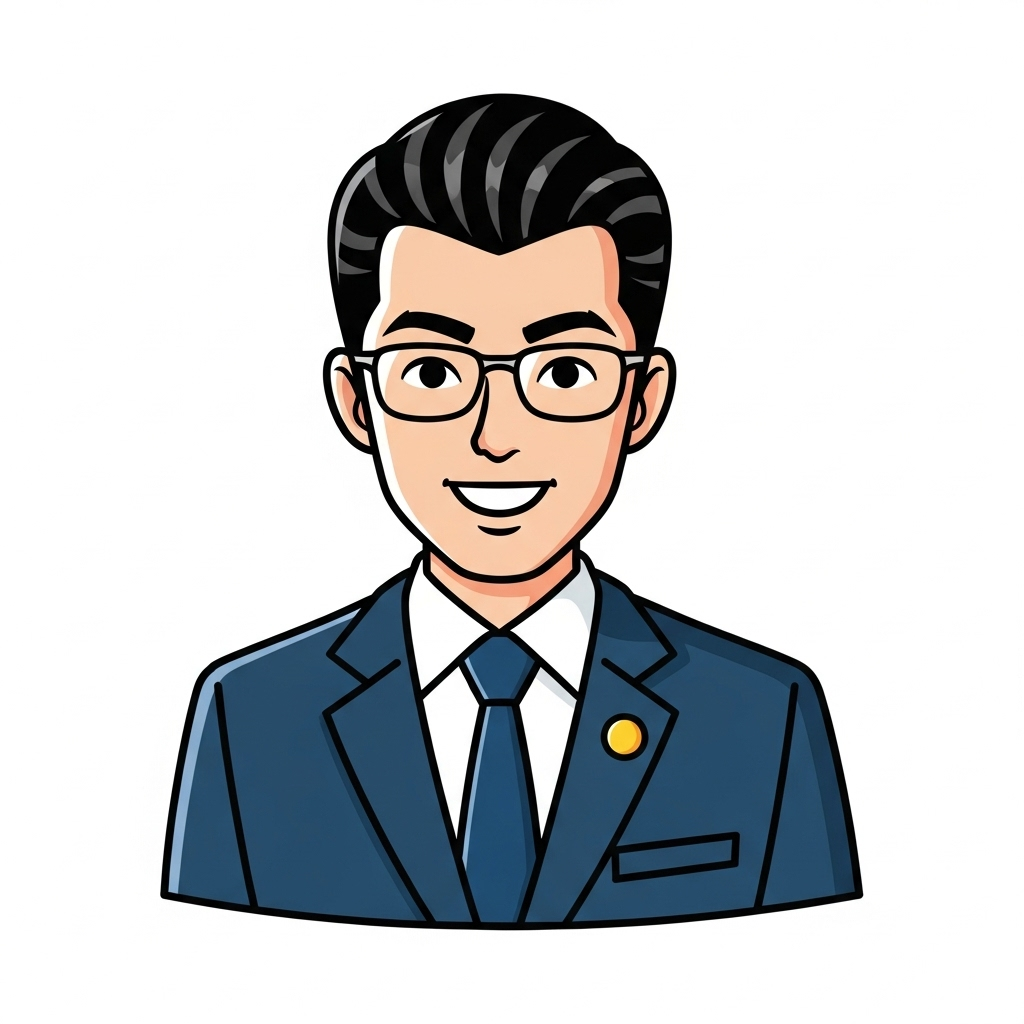
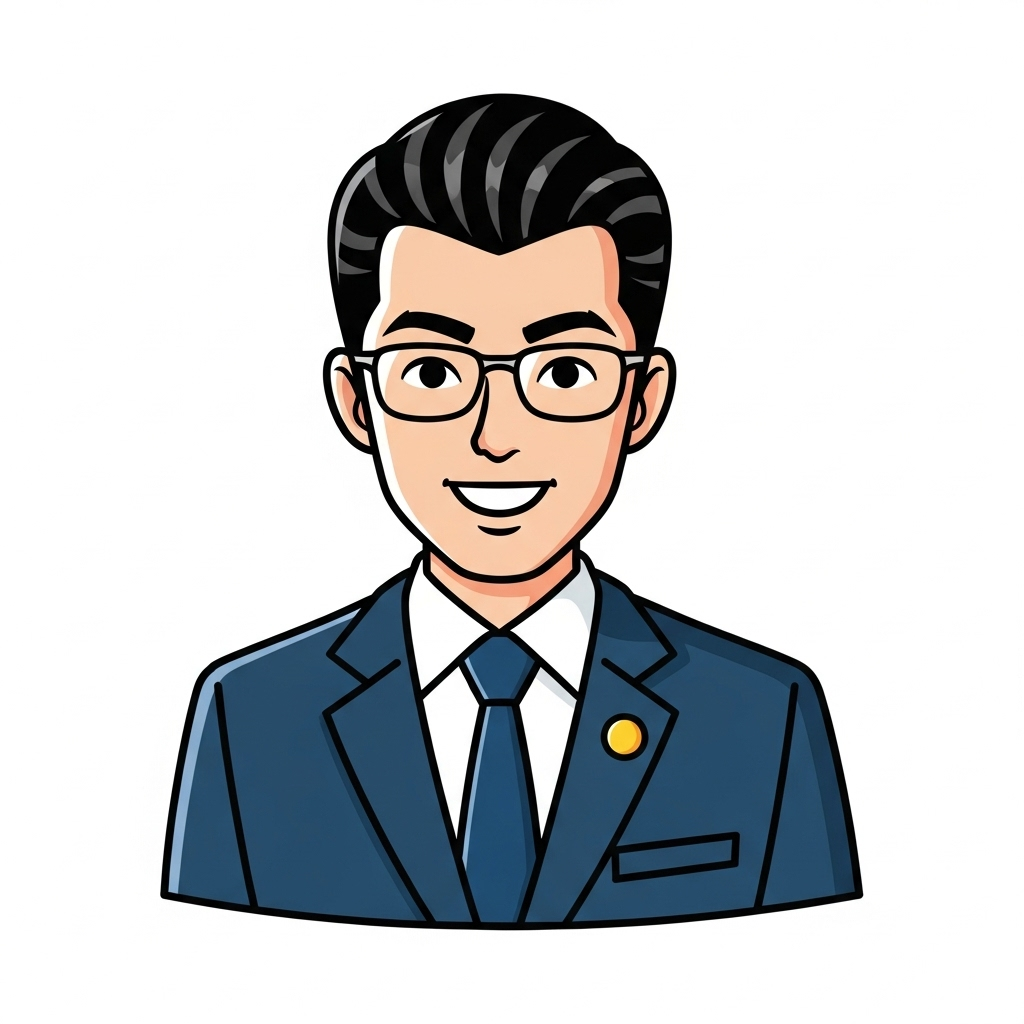
本記事では、技能実習制度と特定技能制度の違いを比較しながら、企業側・外国人側それぞれのメリット・デメリット、必要書類や注意点、職種、外国人の探し方まで詳しく解説します。
目次
技能実習と特定技能の制度比較
| 項目 | 技能実習 | 特定技能(1号) |
|---|---|---|
| 目的 | 技能移転(発展途上国支援) | 即戦力人材の受け入れ |
| 就労可能期間 | 最長5年(1号:1年、2号:2年、3号:2年) | 最長5年(更新制) |
| 日本語要件 | 不問(講習あり) | JLPT N4程度 or 日本語試験合格が原則 |
| 試験 | 不要(実習内で評価) | 職種ごとの技能試験 + 日本語試験 |
| 転職の自由 | 原則不可 | 条件付きで可能(同一業種・在留期間内) |
| 支援義務 | 監理団体が支援 | 受入機関または登録支援機関が支援義務あり |
| 主な対象国 | アジア諸国(ベトナム、インドネシア等) | 特定12ヵ国(協定国) |
企業にとってのメリット・デメリット
技能実習の企業側メリット
- 教育型で比較的コストが低め
- 監理団体が支援してくれるため手間が少ない
技能実習の企業側デメリット
- 実習内容が制限されている
- 原則として転職不可=相性が悪いと続かない
- 不適切な扱いがあると企業が制度停止されるリスクあり
特定技能の企業側メリット
- 即戦力として雇える
- 業務範囲が比較的広く、柔軟性がある
- 長期間の雇用が可能(条件を満たせば5年)
特定技能の企業側デメリット
- 支援業務が義務化(生活支援など)
- 採用までに試験や書類の準備が多い
- 自社で完結させるにはコストと手間がかかる
外国人にとってのメリット・デメリット
| 制度 | 外国人のメリット | 外国人のデメリット |
|---|---|---|
| 技能実習 | 日本で働きながら学べる、手続きは送り出し国が支援 | 日本語力・労働条件に関する自由度が低い |
| 特定技能 | より高い給与、転職の自由、待遇面の改善 | 試験や手続きが複雑、日本語力が求められる |
どうやって外国人を探す?
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 技能実習 | 監理団体が提携している送り出し機関を通して人材を確保 |
| 特定技能 | 海外の試験合格者データベースを活用 or 登録支援機関を通して採用 |
行政書士は登録支援機関としての登録・連携が可能なので、候補者の紹介や制度選択のアドバイスも対応可能です。
必要な書類(概要)
技能実習の場合
- 技能実習計画認定申請書
- 雇用契約書
- 健康診断書
- 教育計画書
- 実習機関の法人資料 など
特定技能の場合
- 技能試験・日本語試験合格証明
- 雇用契約書
- 支援計画書(支援義務がある場合)
- 在留資格変更許可申請書類
- 企業の財務状況資料など
対応できる職種(例)
技能実習・特定技能ともに共通
- 建設業
- 製造業(溶接、機械加工など)
- 食品製造業
- 介護
- 農業・漁業
特定技能のみ
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 宿泊業
- 清掃業なども追加で対象
注意すべき点
- 制度の目的が違うため、雇用の目的と合致する制度を選ぶことが重要
- 特定技能は「支援義務」があるため、登録支援機関と契約することが現実的
- 技能実習では不適切な実習が発覚すると、企業に対する制度停止措置もある
行政書士に依頼するメリット
- 制度選択から手続きまでトータルサポート
- 複雑な在留資格書類の作成・提出を代行
- 監理団体・登録支援機関との調整も対応
- 法務省・出入国在留管理庁との対応もスムーズに
- 必要があれば企業向け説明会・職員研修も実施可能
おわりに
外国人の雇用制度は、適切に選び、正しく運用すれば企業の即戦力人材確保につながります。
逆に誤った制度選択や手続きミスは、トラブルや罰則に発展する可能性も。
だからこそ、外国人雇用のプロである行政書士にご相談ください。
初回相談無料・全国対応可能です。
📞 お気軽にご相談ください
- ✅在留資格取得に関するサポート
- ✅中国語対応可能
- ✅元警察官による信頼と安心の対応
📍埼玉県さいたま市|全国オンライン相談可




メール:info@okonogikei-gyousei-office.com


とよくある質問.png)









-300x251.png)

コメント